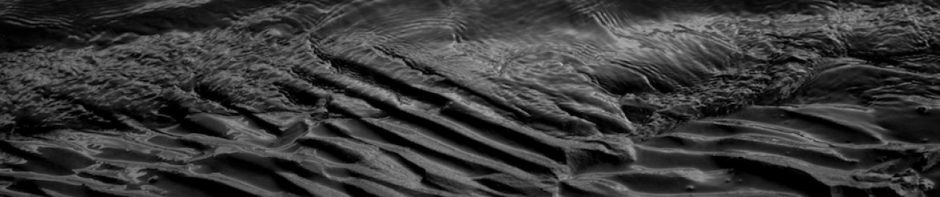kosukesakurai
kosukesakurai-
今日は読影はこれまでとしよう。
03-12 20:40 -
RT @yontengoP: 漫才コンビかな?>藤島氏が真剣な表情でマイクに向かっているときだった。 「スマイル!」(略)藤島氏「このタイミングですか?」。マック赤坂氏「油断しているときにやるのがスマイルだ」【出直し市長選】3候補者、記者会見 http://t.c…
03-12 19:11 -
RT @hiromarine: 大人も泣く RT @DEEPBLUE1219: 夜中にこれが動いてたら子どもが泣くやろ… RT @mujinbot: i-Toad(アイ・トード)。iRobotから発売されたロボット掃除機であるルンバ(Roomba)向けのカバーの一つ http:…
03-12 14:16 -
RT @Isaacsaso: 卒業文集に「報道陣の皆様がこれを読んでいると言う事は、私は既に大きな事件を起こしたのでしょう」って書き出しで書きたすぎるけど、卒業文集書くチャンスもうない
03-12 14:12
-
最近の投稿
最近のコメント
- test に sakurai より
アーカイブ
- 2025年3月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年6月
- 2023年3月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年8月
- 2018年4月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2013年2月
- 2012年9月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年3月
- 2011年11月
- 2011年3月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年5月
- 2009年3月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年4月
- 2006年12月
- 2006年10月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年5月
- 2006年4月
- 2006年3月
- 2006年1月
- 2005年12月
- 2005年1月
- 2004年12月
- 2004年3月
- 2004年2月
- 2004年1月
カテゴリー